Special Interview
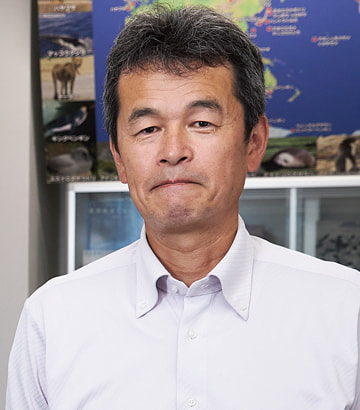
東京大学大気海洋研究所
海洋生命科学部門行動生態計測分野 教授
佐藤 克文 氏
1990年 京都大学農学部水産学科卒業。92年 同大学院農学研究科修士課程水産学専攻修了。同大学院農学研究科博士後期課程水産学専攻に進学し、95年に同大学農学博士授与。国立極地研究所の助手を経て、東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター准教授に。2014年から現職。現在、岩手県大槌町の大槌沿岸センターを中心にバイオロギングによる動物の生態調査などを行っている。
研究も人生も想定外のことばかり。だからこそ面白い
野生動物に小型の計測器を取りつけてデータを記録する「バイオロギング」という手法を用い、世界の海でペンギンやアザラシなどの水生動物の生態を調査してきた佐藤克文氏。柏キャンパスの大気海洋研究所で日々研究に励む佐藤氏に、その楽しさと可能性を聞いた。
意地で続けた研究が予期せぬ結果を発見
海の中には、解明されていない謎がたくさんあります。私は30年以上にわたりその謎に向き合い続け、海鳥、ウミガメ、アザラシ、ペンギンなどの動物を対象に調査・研究を行ってきました。
広く深い海で暮らしている野生動物を観察するのは容易なことではありません。そこで編み出されたのがバイオロギングという手法です。この手法により、周辺の環境情報を記録、モニタリングし、水生動物の行動や生態をより詳細に調べることができるようになりました。
といっても、バイオロギングは想像通りにはいかないことの連続です。思い返せば、私の人生も思い描いていた通りにいかないことばかりでした。
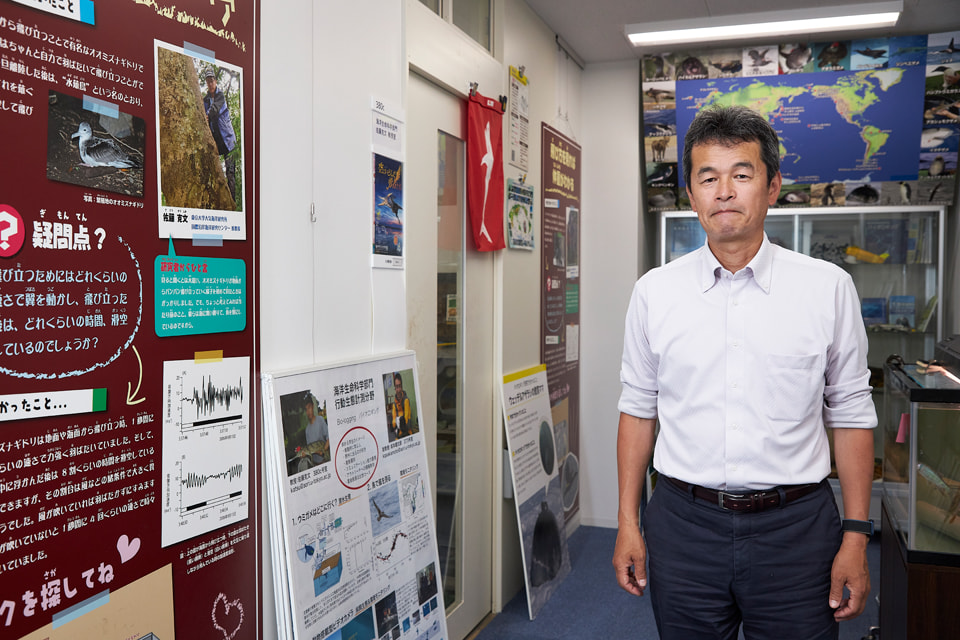
大学でも、「こんなはずじゃなかった」と意気消沈していた時期があります。子どもの頃から釣りが好きで、“お魚博士”を目指して大学では水産学科に進学したのですが、いざ入学すると想像とは全く違っていました。水産学科では毛針の色や形による釣れ方の違いを試したりするのだと勝手にイメージしていたのですが、「それは半世紀以上前の研究だ」と言われて(笑)。
当時はバイオテクノロジーの萌芽期で、生物の謎を遺伝子レベルで解明することが最先端の研究でした。でも、肉眼で見えないほどミクロなことを調べるのは、私には魅力的には思えず、内心「しまったなぁ」と思っていました。そんなこともあって、学部時代は勉強にあまり身が入らず、サッカー部の活動に熱中していましたね。
転機が訪れたのは、4年生になったときです。所属する研究室を決める際に、先輩からウミガメの背中に計測器を取りつけてモニタリングすることがあると聞き、一気に興味がわきました。これが、バイオロギングとの出合いでした。
でも、肝心の卒業研究はうまくいかなかった。ウミガメは2週間ごとに同じ砂浜に戻ってくるといわれていたので、ウミガメの体につけた装置を回収してデータを分析する予定だったのですが、1匹は漁師さんの定置網に引っかかってしまい、もう1匹は戻ってこなかった。それが悔しくて、「このままじゃやめられない」と大学院に進んだのです。
だから大学院に入ったばかりの頃は、研究者を目指そうと決意していたわけではなく、意地でやっていたようなものでした。そして、修士課程2年目のとき、装置のつけ方を工夫してみたところ、ウミガメ4匹のすべてのデータを集めることができたのです。それまでの取りつけ方ではウミガメへの負担が大きかったことが、同じ浜に戻ってこなかった原因のひとつと考えられました。
さらに、ウミガメの背中と胃の中に取りつけた装置から得たデータは、思いがけないことも教えてくれました。ウミガメは海の深くまで潜ってエサを探します。深いほど水温は下がりますが、エサを食べると一時的に胃内の温度が上がります。そこで、胃内の温度を記録することで、エサを食べるタイミングや回数がわかるのではないかと考えました。
ところがデータを取ってみると、産卵期のウミガメはエサをほとんど食べないことがわかり、当初の目論見は外れてしまいました。ですが、温度変化を見ると、背中で測定した水温は深さに応じて下がるものの、胃内で測定した体温は一定の値を保っていました。ウミガメは爬虫類なので変温動物だと教科書には書かれていますが、体の中心部の温度は一定だったわけです。結局、それが私の博士論文のテーマになりました。
このように、研究では当初の思惑から外れて予期せぬ結果が出ることがしばしばあります。そこにストレスを感じる人もいますが、私は自分の想像を超えることが起きるほうが楽しく、それが性格的に合っていたのだと思います。論文が国際誌に掲載されたこともあり、「研究者として生きていこう」と思えるようになりました。
バイオロギングを通じて動物と人間のよりよい関係を築きたい
1997年に国立極地研究所の助手になり、南極でアザラシやペンギンの調査を行っていましたが、ここでも予想外のことが起きました。アザラシはエサを取るために 300メートル近く潜ると聞いていたのに、背中に取りつけた装置を回収したところ、授乳期のメスは全然潜っていなかったんです。
そこで試しに、前向きにつけていたカメラを後ろ向きにしてみると、生後4週間のアザラシの子が、母アザラシの後を泳いでいる映像が撮れた。アザラシがエサを取る以外の目的で泳ぐことなど想像もしていませんでしたが、実際には浅いところで赤ちゃんに泳ぎ方を教えていたことがわかったんです。
極地研究所で調査に打ち込む日々は楽しかったですよ。しかし世界の国々の研究を見ているうちに、考えが変わりました。たとえば南極のアメリカ基地に行くと、その一帯で生まれた個体すべてに標識をつけて30年以上にわたって追跡調査を行っているんです。私もそういう長いスパンで観察できるフィールドがほしいと思いましたが、南極など毎年行けるわけでもない。
そのため、国内でいい調査地がないか探していると、たまたま東大の海洋研究所(現・大気海洋研究所)国際沿岸海洋研究センターの准教授のポストがあった。そこから岩手県大槌町にある大槌沿岸センターで、オオミズナギドリやウミガメなどの調査を行うようになったのです。

東北海洋生態系調査研究船「新青丸」からフライトレコーダーを搭載したオオミズナギドリを放鳥する佐藤教授
大槌が面する三陸沿岸は親潮と黒潮が混じり合うため、多種多様な生物が生息し、調査にはうってつけの場所でした。ところが、東日本大震災で研究所が甚大な被害を受けたのです。私はオーストラリアに出張中で、大槌に残っていたメンバーも無事だったのですが、建物の3階まで津波が来て、資料や機材などはすべて流されてしまった。ただ、調査データを私の手持ちのパソコン上にデジタルで残していたのは不幸中の幸いでした。
その後、津波前後の動物を調査したところ、ほとんど被害を受けていないことがわかりました。たとえば鳥の巣は、津波が届かない場所にあったために難を逃れていました。三陸地方は昔から何度も大地震に見舞われており、低い土地に営巣する鳥は淘汰され、高いところに巣をつくる個体だけが生き残ったのかもしれません。
私がいま力を入れているのは、バイオロギングのデータを収集し、誰でもアクセスできるデータベースを作ることです。海水温の変動を気象予測に役立てたり、ウミガメがプラスチックゴミを食べる瞬間を捉えた映像で環境教育を行ったり、データを活用して動物と人間のよりよい関係を築いていければと考え研究を続けています。








